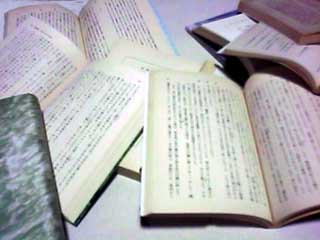小説
先週、中島梓さんの「夢見る頃を過ぎても」という文芸時評を読んだ。歯に衣着せぬ口調はとても爽快で、読んでいて気持ちが良かった。
ここ半年くらいほとんど本を読んでいなかったので、友達にお薦めの人を聞いて電車の中などで読むことにした。
本を開けてみて、文芸時評であることを知った(いったい、僕はどういういう本の選び方をしているのだろう)。批評とかはあまり好きではないので、最初はしまったと思った。
中島氏も文中でこの作業はつまらない、と言っているように最初の一部は読んでいてもむちゃくちゃ面白い物ではなかった。
しかし、読み進んで行くうちに、おもしろくなり、中島氏の言いたい事が見えてきた。それはとても明白で「小説家達は、どういう読者に、何を訴えたいのか」ということだ。小説にしろ、写真にしろ、何にしろ、個人が情報を発信するときは必ず、相手がいて、言いたい内容があるはずだ。しかし、現代の「純文学」の作家の多くは誰に何を伝えたいのかが分からない、という。
その背景には、中島氏がとことん小説が好きなことがある。中島氏は文中で「かつて、私が文学に助けられた文学少女だったから」と言う。さらに、文学は、今の少女達に何をもたらしているのか、と訴える。
僕も中学以来、小説、エッセイなどと関わってきた身として、色々なことを考えさせられた。しかし、少なくとも僕は中島氏の危機意識の一部は持っていた。ただ、中核である「小説を読むことが人を救う」事は今まで考えたことがなかった。それは、僕が読み手ではなく、書き手から文章に携わり始めたからかも知れない。そして、僕は逆に文章を書く行為に助けられてきているのかも知れない。すくなくても、今の僕を作り上げている要素のひとつに文章を書くと言うことがあるのは間違いない。
中島氏の指摘は職業小説家だけでなく、僕らのような素人小説家や他の媒体で何かを伝えようとしている人が常に考えていなければならないことだと思う。
中島梓『夢見る頃を過ぎても』ちくま文庫
もどる